【新春インタビュー】 二人の日本画家に聞く 上村淳之×田渕俊夫
【新春インタビュー】 二人の日本画家に聞く 上村淳之×田渕俊夫
絵は個人のもの感動で描く
田渕俊夫(日本美術院同人・代表理事)
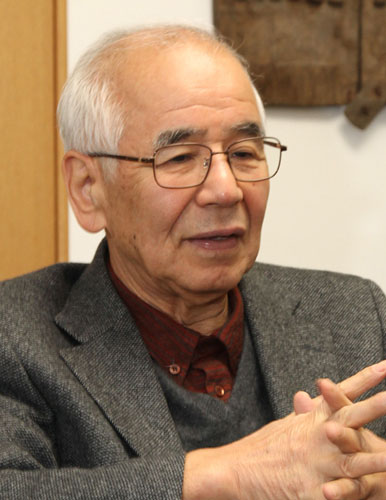
1941年東京生まれ。67年東京藝術大学大学院日本画専攻修了。68年再興第53回院展に初入選し以降、院展を中心に制作発表を続ける。その後、愛知県立芸術大学、東京藝術大学で教鞭を執り、現在は日本美術院同人・代表理事を務める。風景、植物などのモチーフを線描を生かした構成的な作品で知られる。
東京藝術大学で受けた指導
東京藝術大学に入学したのが1961年、20歳になる年で、教授陣らは須田珙中、田中青坪、岩橋英遠、吉田善彦、吉岡堅二の錚々たる方々でしたが、何を教わったかと言えば「実はほとんど教わっていないんですよ」。例えば滲み止めの礬砂の作り方についても、「膠の色はだいたいこの位かな、そこに乳鉢で粉にした明礬はこの位かな」という教え方だったんです。今でしたら、「三千本膠は何本に明礬何グラム」という教え方をすると思うんですけれど。さらに絵の具の溶き方は平山郁夫先生に教わったんですが、「皿のなかで筆を使って混ぜる人がいるが指で丁寧に溶きなさい」と私たちの頃はそういう指導を受けました。
それでは何を教わったのかと言えば、絵が出来上がると研究会を開いて批評を受けるんです。「田渕君のは途中で見たときは良かったけれど出来上がってがっかりしたね」と非常に厳しかったです。そして後で分かることなんですが、絵は個人のものですから、失敗をさせるんです。失敗をすると、「ああこれでは駄目だ」とやり方を自分で開発し覚える。さらに、18、19歳で東京藝大に入学した学生は言ってみればその年代のトップの学生なんです。その才能ある人間を下手に指導すると個性を無くし、自分で考える能力を失うことになるんです。その代わり学生は、公募展などで先生の発表する絵を見て「ああ凄い先生なんだ」ということを学んでいく訳です。
もともと明治以前の絵画は真似なんです。パターンがありそれを踏襲し、流派があって、大将がいて絵を請負うと弟子たちが寺院や城内の絵を描く訳です。すると個性がばらばらだと困ってしまう訳です。そこで、同じ技術を身に付けさせる模倣から始まるんです。ヨーロッパでもルネサンス期のラファエロなどは100人以上の弟子がいたと言われています。ところが、明治以降は個性を大事にするようになった、ということですね。
愛知芸大での出会い

「青木ヶ原」 1969年 162.0×228.0cm 紙本彩色 愛知県美術館蔵
30代になると愛知県立芸術大学で片岡球子先生の下、学生に日本画の指導をする立場になりました。片岡先生は長い間小学校に務め、後に女子美、愛知芸大へと赴任されましたが、「絵の指導は訓導だ」と仰いました。それは、小学校の生徒を教えるように、「何も分からない人は一から教えて行くのが教育だ」という信念がありました。例えばヌードデッサンは塊で描けという。またある時、動物制作が出来上がり鳥の絵を批評することになりました。私が「この鳥は飛べませんね」と言ったら、片岡先生は「どこが飛べないのよ、はっきり言わなければ学生は分からないじゃない」と言われたこともありました。しかし、東京藝大に戻る時に「本当にあんたの言っていたことは正しかった」という言葉を頂き、学校によって、先生によって、教え方は違うなあと思いましたね。
「院展的でない、自己流の絵」
院展に初入選をした翌年、再興第54回院展に出品した「青木ヶ原」で再び入選をすることができました。この作品は初期の私の人生、作品の方向性に転機をもたらすことになりました。一つは、出品にあたり助言を頂いたある先生から「院展は色を塗っていないところがあると落とされるよ」という言葉を掛けられましたが、私はどうしても色ではなくて線だけで表現をしたい部分があり、思い切って出品をしたところ、以外と良い評価を頂いたんです。それ以来、「院展的でない、自己流の絵を描こう」という思いで描いてきました。結局は「自らが感動して描いた絵、感動が無ければ、人に感動を与えることは出来ないのではないか」ということが私の信念となりました。つまりは「感動さえあれば、人物でも、風景でも、植物でも何にでも絵になる」ということです。そしてその中でふと気付いたことは「永遠に続く何か」ということなんです。
例えば明日香に行っても現在は農村風景である場所に過去には万葉人がいたり、歌を詠んだり、恋をしたり、都があったと思うと、単なる風景ではなくなる。気が付いたら自分は大地悠久の歴史を描いているのかなと思うようになったり、植物を描いてもすすきの一生やあさがおの一生を描いたり、結局は永遠の繰り返しを見ているのかなあと思うようになりました。その上で絵を描くということは、自らが演出家のような思いになって、見たものそのものを描くのではなく、四角い画面のなかに別の方向性で描いて来ているように思います。しかし、それが何なのかは具体的には分かりません。永遠に分からないかもしれませんが、一種の本能のような、しかしそれを表現するにはかなりの技術や力が必要で、総合力で絵は出来ると思います。

「爛漫」 2003年 171.4×364.0cm 紙本墨画、四曲一隻屏風 今治市大三島美術館蔵
色彩と墨への思い
最初は色のある世界を描いていた訳ですが、下図を徹底的に描いて計算し画面を作り上げていくと色より形、つまり線は強いなあと思うことがあって、色はごまかせるなあと思うんです。そして最後には単純明快な墨の世界が私の日本画家としての最終目標と思っていました。そこへ永平寺に続き、鎌倉八幡宮、智積院などで襖絵を描く機会を頂きました。そして今、墨は色彩以上に効果があるということを考えています。例えば墨で描いた桜の絵があるのですが、その絵を見て「桜がピンクに見えた」と言われたことがありました。桜の本質を追求し表現すると、見る人の心に色が見えてくるのではないかと思います。現在は大学を定年し、制作三昧の日々です。制作三昧と言えば優雅な生活をしているように思われますが、ところが「三昧」という言葉を辞書で引きますと実は「必死にやる」ということなんです。まさにそれがなければ絵は描けないと思います。
再興から100年を迎える日本美術院
1914(大正3)年の再興から100年を迎えるにあたり、院展の歴史は明治以降の日本画の歴史、つまり単なる院展の歴史ではなく近代日本画の歴史なんです。東京都美術館で開催される特別展「世紀の日本画」(1・25~4・1)では日本美術院の物故作家と現役作家がともに同会場で展示されます。ここで大事なことは、101年目に向けて現役の同人がどのくらいの絵を描いているか、もう一度見詰めることなんです。現役作家は院展の同人になるきっかけとなった大観賞(日本美術院賞)受賞作に絞り出品をします。100年で院展同人は日本画で103人でしかなく、一年で一人でるかどうかという厳しさなんです。現役の同人は32人ですが、今展に選ばれない作家もいます。それが何を意味するかは今後110年、120年に向けて作家として残れるか、つまりは恥ずかしくない絵を描くため、制作三昧でいきましょうということなんです。(了)
【関連リンク】
「新美術新聞」2014年1月1・11日合併号(第1332号)5面より
関連記事
-
02/28 10:00
-
01/31 12:00
-
12/27 10:00
-
03/11 10:02
-
02/28 10:00
-
01/31 12:00
-
12/27 10:00
-
12/05 10:40


